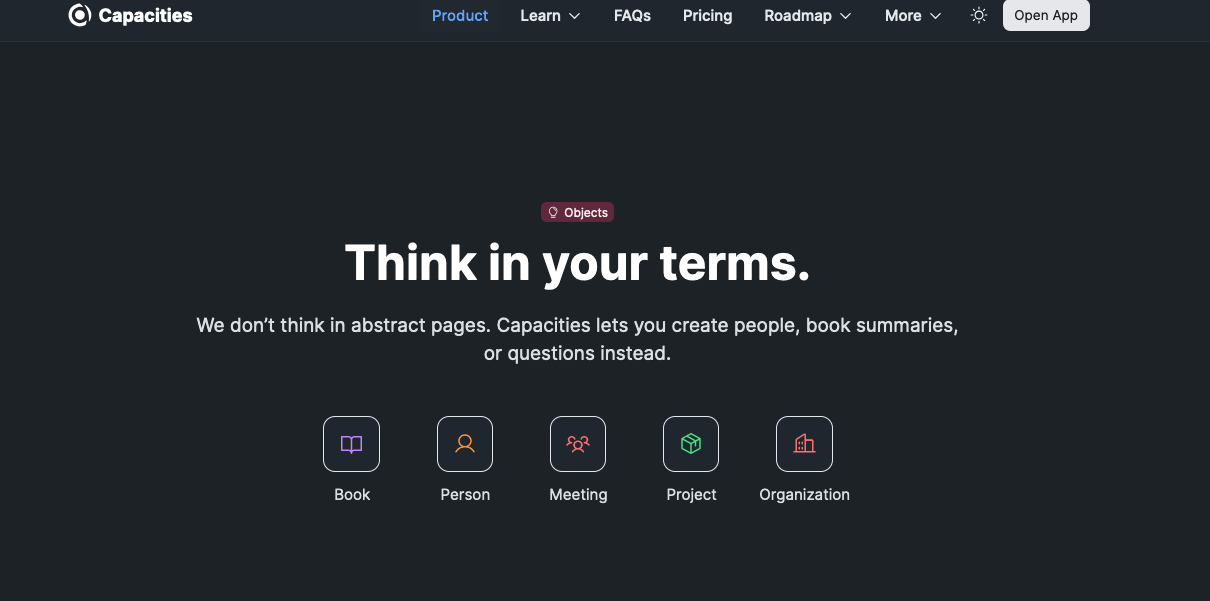「ベーシック」と呼べるデジタルノートツールを考えようとした場合、次の二つのポイントが気になります。
簡易に使い始められること
安価で使えること(可能ならば無料で)
最終的に行き着く先のツールが上記を満たさなくても構いません。でも、一番最初に触るならばこのポイントは大切だと思います。
この点を考慮して、いくつかのツールをピックアップしましょう。
Notion
ごく普通に考えて、無料で使える多機能のデジタルノートツールと言えばNotionです。
デジタルノートとしてやりたいことのほとんどはこのツールで実装されています。しかもデータベースの作成及び利用が簡単に行えるので、いわゆる「デジタルらしい情報処理」にも向いています。AI機能の開発も活発であり、将来性も十分に期待できます。
将来性に関して言えば、フリーミアムモデルがいつまで存続できるのかという疑問が──かつてEvernoteがたどった歴史を加味すると──あるでしょう。もちろん、ビジネスがどう推移するのかは誰にもわからないので確定的なことは何も言えませんが、それでも「ある程度は大丈夫ではないか」という感覚があります。なぜなら、はじめからビジネスユース=有料のモデルと共にスタートしているからであり、さらにAI機能を利用する場合はそこでサブスクリプションが発生するからです。言い換えれば、ユーザーの総数がどんどん増えていけば、そのうちの何%かが有料会員になってビジネスが成長する、という単純な構図にはなっていません。「お金を取る場所」がきちんと設定されている印象です。その意味で、人気になってユーザー数が増えたけども、その人たちはどれほど使ってもお金を払うことが無く、ビジネスモデルに負担を与える、みたいなねじくれた状態は起きにくくなっていると想像します。
とは言え、ユーザーからするとAI機能の利用を念頭に置くなら無料で使えるツールではなくなることも意味します。Notion AIにお金を払い、生成AIツールにもお金を払うとなってくると負担の大きさはバカにはならないでしょう。
その意味で、「AI機能を使わない範囲での利用」がベーシックデジタルノートツールとしてのNotionという感じになるでしょうか。
Obsidian
もう一つの有力な選択肢がObsidianです。
ある分野ではものすごく知られています。というよりも古き良きライフハッカーな人たちはNotionよりもObsidianを好む傾向があるようです(その感じはなんとなくわかります)。
そのObsidianは以下の特徴を持ちます。
ローカルファイルベース
マークダウン記法
有志によるプラグイン開発
決定的なのが、デジタルノートツールでは珍しくクラウド型ではないことです。サブスクリプションでクラウド連携すること自体は可能ですがそれはオプションであり、必須ではありません。何もしなければ、自分のパソコンにファイルを置くだけで済みます。
まずこの点が古き良きライフハッカーに好まれている点でしょう。その世代の人達は「名前をつけてファイルを保存」に親しんできた人たちであり、場合によっては自分でコマンドラインを触り、ファイルを編集してきた人たちだからです。そういう情報の扱い方のほうが馴染みがある。
逆に生まれたときからクラウドツールが当たり前の人にとって、「名前をつけてファイルを保存」はメンタルモデルとしてあまり馴染みがないものであり、Notionなどの方が使いやすい・触りやすいということは十分考えられます。
そのどちらがよいのかは、ほとんど思想的対立とも呼べる議論を含むのでここで断じることはできません。どちらもメリットはあるので、最終的にはユーザーの好みと思想の問題です。
とりあえず、ローカルファイルを使ってデジタルノートできるのがObsidianの特徴です。
また、それと関係して記法はマークダウン記法を直接使います。スラッシュコマンドなどでフォーマットを呼び出すのではなく、テキストファイルにそのまま見出しの記法やリンクの記法を書くわけです。
このマークダウンも賛否両論あるわけですが、最近では構造的文章のデファクトスタンダードになりつつある風潮も感じます。ようするに複数の見出しで構成させる文章を、リッチテキストエディタを使わずに簡易に記入できたら便利だよね、という話で、一度マークダウンで書いておくことで、それをWord形式に変換したり、プレゼンテーション用のスライドに変換したりといろいろ使い勝手があがります。それもこれも、マークダウンによって変換されるHTMLがそもそも構造的な文章だからです。
私たちはあまり構造的に文章を書く訓練をしてきていませんが、それでもHTMLやらマークダウン記法の利用に慣れることでそういう”作法”も身近になるのかもしれません。
最後の「有志によるプラグイン開発」ですが、Notionでもテンプレートの共有ができるのですが、Obsidianの場合Obsidian本体の機能にまでタッチできるのが大きな特徴でしょう。見た目だけでなく、機能もまた第三者が提供するプラグインによって拡張されます。これはとてもライフハック的な感覚です。
Cosense
次はCosenseです。少し前まではScrapboxという名前で呼ばれていました。
個人ユースなら、公開・非公開プロジェクトのどちらでも無料で使えます。Notionのような多機能さはありませんが、テキストを記入し、リンクしていくという使い方においては右に出るツールはありません。
最近はinfoboxという機能によって、入力した情報をデータベース的に(事後的に)利用することもできるようになりました。
でもって、一人で使うだけでなく、複数人で情報・知識・知見を持ち寄るツールとしてもたいへん便利に使えます。
おそらく利用の簡単さで言えば、このCosenseが一番簡単でしょう。アカウントを作れば、あとはページを作っていくだけです。ややこしい設定はまったくありません。だからといって単純な利用しかできないわけではなく、UserScriptを使えばかなりひねった使い方も可能です。
Capaticies
今回紹介する最後のツールがCapacitiesです。
それまでのノートツールが注目してこなかった「オブジェクト」という考え方を中心に据えたデジタルノートツールです。
おそらくここまで紹介してきたツールの中で一番「Evernoteっぽい」のはこのツールでしょう。Evernoteのノートブックが、中に保存される情報に合わせてビュースタイルを変更できるようになった、みたいな感覚が近しいかもしれません。
自分なりの整理の軸・体系をしつつ情報をデジタルで保存していく、というのがこのCapacitiesのわかりやすい使い方です。
現時点で無料で問題なく使えますが、今後の展開によっては無料プランの機能が制限される未来は十分予想できます。その点には注意して利用を開始するとよいでしょう。
さいごに
というわけで、今回は「とりあえず無料で使えるデジタルノートツール」という観点を中心にベーシックなデジタルノートツールを挙げてみました。
Notion
Obsidian
Cosense
Capacities
それぞれのツールについては、また別の投稿で詳しく掘り下げていきましょう。料金が必要になるその他のツールの紹介などは、以下の電子書籍をご覧ください。